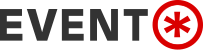秋季特別展「ジャパニーズ・ヴィーナス―彫刻家・藤井浩祐(こうゆう)の世界―」
※掲載中の情報は調査時の情報となります。
※必ず公式サイトなどで最新の情報をご確認ください
- ★開催日・期間
- 2014年08月29日(金)〜2014年10月19日(日)
- ★開催場所・会場
- 井原市立田中美術館
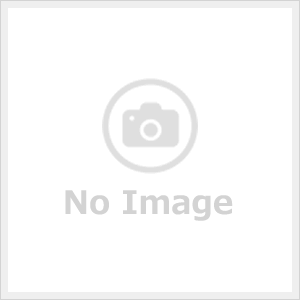
再興日本美術院(院展)黎明(れいめい)期の20年間、10歳年長であった木彫の平櫛田中と共に、彫塑の主軸として活躍した藤井浩祐は、優美な裸婦像で広く知られました。
藤井浩祐(1882~1958、のち1953年より浩佑)は、明治15年(1882)に東京神田錦町に生まれ、東京美術学校に入学して彫刻を学びました。卒業後、文展にロダン風の写実的な表現手法に基づきながら、炭坑で働く人々など社会の底辺に生きる労働者に目を向けた作品を発表して注目を集めます。
大正5年(1916)、日本美術院の同人に加わり、昭和11年(1936)に脱退するまで、平櫛田中(1872~1979)とともに彫刻部の主軸として活動を行うと同時に、こうした展覧会芸術にとどまらず、建築装飾や全国中等学校野球選手権(現・全国高等学校野球選手権大会)の大会参加章を制作するなど、社会との接点を求めた活動も積極的に行いました。
また、美術に関する執筆も多く、美術雑誌における展覧会評をはじめ、彫刻の技法・啓蒙書である『彫刻を試る人へ』(中央美術社、1923年)などによって、同時代の美術関係者、彫刻志望者たちに大きな影響を与えました。
さらに大正期に、その頃全国的に拡がりをみせた児童教育の変革運動を承けて、東京府内(現・東京都内)の小学校で自らの考えに基づく「自由彫塑」の指導を実践しています。
このように生前の浩祐は彫刻の普及にも大きく貢献し、昭和12年(1937)に帝国芸術院の会員(戦後は日本芸術院会員)に選ばれていますが、アトリエが戦災で焼失し、主だった作品が失われたことも災いして、今日まで十分な検証が行われたとは言い難い状況にあります。
初の本格的な回顧展である本展では、日本における美の女神の創造を生涯の理想とした藤井浩祐の歩みを折々の代表作でたどりつつ、彫刻を中心とする彼の幅広い領域の活動を紹介し、近代日本彫刻史における業績を顕彰いたします。
| 開催地 | 井原市立田中美術館 |
|---|---|
| 開催期間 | 2014年08月29日(金)〜2014年10月19日(日) イベントによっては、期間中でも休みの日がある可能性があります。必ず公式ページでご確認ください。 |
| ホームページ | http://www.city.ibara.okayama.jp/denchu_museum/exhibit/exhibit_history/201408.html |
| 料金 | 【入館料】 一般:700円(560円) 65歳以上:350円(280円) 高校生以下 無料 ※( )内は20名以上の団体料金 |
| お問い合わせ先 | 0866-62-8787 |
| 備考 | 【開館時間】 午前9時~午後5時(入館は午後4時30分まで) 8月29日(金)は開会式が行われるため、10時30分より開館。 【休館日】 月曜日(ただし、祝日は開館し、翌日休館) 【出品作品】 《トロを待つ坑婦(こうふ)》第8回文展出品・東京国立近代美術館蔵、《背を拭く女》再興第13回院展・新潟市美術館蔵、《捕球の刹那》野球殿堂博物館蔵、《梳髪》第1回新文展・東京国立近代美術館蔵、《臥裸婦》東京藝術大学大学美術館蔵(平櫛田中旧蔵)、《浴女》茅野市美術館蔵、《鏡》第2回新文展・京都市美術館蔵などブロンズ作品を中心に、初期の名作として知られる大理石像《譚(たん)》第6回文展・東京国立近代美術館蔵、積極的に用いた新素材のセメント彫刻《裸婦》紀元二千六百年奉祝展・碌山(ろくざん)美術館蔵、ブロンズに鋳造せず石膏を完成作にしたと考えられる《裸婦》(笠間日動美術館蔵)や、貴重な石膏原型、愛犬家として著名であった浩祐の面影を伝える犬をモチーフにした作品、妻の実家であった銀座木村家の名物をブロンズ彩色で作った《あんぱん》など多彩な素材と主題を縦横に用いた名品80数点を展示します。 【イベント】 藤井浩祐展 記念講演会 <事前申込不要> 「藤井浩祐の彫刻の美しさ」 講師 田中修二氏(大分大学准教授) 期日 9月14日(日) 13時30分~15時 会場 井原市民会館 鏡獅子の間 |
情報更新日:14/07/31
岡山の1ヶ月以内に開催されるイベント情報
イベント一覧岡山のイベント情報を検索!
★イベントを探したい日付をクリックしてください!