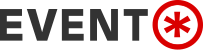第73回企画展 「台湾平埔族(へいほぞく)のものがたり ―歴史の流れと生活文化の記憶―」
※掲載中の情報は調査時の情報となります。
※必ず公式サイトなどで最新の情報をご確認ください
- ★開催日・期間
- 2014年10月08日(水)〜2014年12月08日(月)
- ★開催場所・会場
- 天理大学附属天理参考館(奈良県天理市守目堂町250番地)
”平埔族(へいほぞく)”とは、もともと台湾の西部平野に住んできた先住民族の総称です。彼らは17世紀後半から中国大陸より移住してきた漢民族の影響を受け、独自の言語や生活文化は大きく変容、または失うことになりました。台湾では1980年代からの民主化に伴い、先住民族の伝統文化を保護し、自らのアイデンティティを探ろうとする動きが活発になっています。本展では絵図、古文書などから彼ら平埔族の歴史を振り返り、今では台湾現地においても見ることが難しい生活文化資源を紹介します。さらに、現地調査で撮影した記録写真を通して、今日の平埔族の人々の姿にも迫ります。
| 開催地 | 天理大学附属天理参考館(奈良県天理市守目堂町250番地) |
|---|---|
| 開催期間 | 2014年10月08日(水)〜2014年12月08日(月) イベントによっては、期間中でも休みの日がある可能性があります。必ず公式ページでご確認ください。 |
| ホームページ | http://www.sankokan.jp/exhibition/plan/73.html |
| 備考 | 2014(平成26)年10月8日(水)~12月8日(月) 当館3階企画展示室1・2 |
情報更新日:14/09/03
平埔族(へいほぞく)は、台湾原住民のうち西部の平野部に住む民族を指す総称である。清朝の統治下には「平埔番」、「熟番」などの蔑称が用いられていた。山地に住む原住民である高山族と区別されるが、これは居住地域から便宜的に用いられるものであり、正確な民族系統を反映したものとはいえない。
元々は、台湾の平野部全域に居住していた。しかし、明代以降、特にオランダが漢人を労働力として移入させてから、漢人との通婚や漢化が進んだ。特に清朝は政策として漢化(漢文化化)を推し進めた。そのため、徐々に平埔族を名乗る者は減少していった。日本統治時代に平埔族についての研究が始められたが、既に大多数は漢人化していた。第二次世界大戦後、中国国民党が台湾を支配した後は、再び漢化政策が行われ、エスニックグループとしての意識が希薄化し、また政府も原住民として認定しなかった。
民主化後、エスニックグループに関する研究が盛んになると、社会や学会などの注目を集めるようになった。現在、サオ族とクバラン族のみが政府から原住民族としての認定を受けている。その他にもケタガラン族など、認定を受けていないグループが多い。
「平埔族」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』
2013年3月09日07:17 UTC
http://ja.wikipedia.org/wiki/平埔族
奈良の1ヶ月以内に開催されるイベント情報
イベント一覧奈良のイベント情報を検索!
★イベントを探したい日付をクリックしてください!