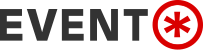黎明館企画特別展「南からみる中世の世界~海に結ばれた琉球列島と南九州~」
※掲載中の情報は調査時の情報となります。
※必ず公式サイトなどで最新の情報をご確認ください
- ★開催日・期間
- 2014年09月27日(土)〜2014年11月03日(月)
- ★開催場所・会場
- 鹿児島県歴史資料センター黎明館(鹿児島県鹿児島市城山町7-2)
終了芸術・デザイン
南九州から台湾に至る南北1200kmの海域には,先島諸島,沖縄諸島,奄美諸島,トカラ列島,薩南諸島からなる琉球列島が連なっています。中世日本の支配領域の周縁にあって,謎に包まれた琉球列島の歴史は,喜界(きかい)町城久(ぐすく)遺跡群などの発見を契機として,今,全国的な注目を集めています。
中国の宋(北宋980~1127,南宋1127~1279)の時代,活発化する東シナ海交易のうねりは,11・12世紀,博多を拠点とする日宋貿易を興隆させ,列島内に広範な交易のネットワークが広がりました。
その波は琉球列島の中・南部にも及び,中国産の白磁碗,徳之島産のカムィヤキ,西北九州産の滑石(かっせき)製石鍋(いしなべ)の流通にみる広域の流通圏と文化的なつながりが生まれます。グスクを拠点に地域の有力者(按司(あじ))が割拠するグスク時代が始まり,やがて三山(北山,中山,南山)の抗争を経て琉球王国が建国されます。
この企画特別展では,平安時代後期から鎌倉,南北朝時代に至る南九州・琉球列島に視点を置き,「唐物(からもの)」として珍重された貿易陶磁や国産交易品,文書史料を手がかりに,人々が海洋を舞台に躍動した時代の「ひと・もの・文化」の交流を紹介します。
| 開催地 | 鹿児島県歴史資料センター黎明館(鹿児島県鹿児島市城山町7-2) |
|---|---|
| 開催期間 | 2014年09月27日(土)〜2014年11月03日(月) イベントによっては、期間中でも休みの日がある可能性があります。必ず公式ページでご確認ください。 |
| ホームページ | http://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/kouza/jisyukikaku/kikaku_tokubetutenji/event_chuseinosekai.html |
| 料金 | 【観覧料】 一般800円(600円) 高校・大学生500円(350円) 中学生以下・障害者無料(身体障害者手帳,療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の提示のあった方と,その介護者1名は免除) ※()は前売り券,20名以上の団体割引料金 ※県内の高校・特別支援学校の高等部の生徒とその引率者については,教育課程に基づく学習活動として入館する場合は,観覧料は免除(事前の申請が必要) 【前売り券発売所】 黎明館総合案内,山形屋プレイガイド,生協コープかごしま各店サービスカウンター,アミュプラザ鹿児島・マルヤガーデンズの各インフォメーション,鹿児島県職員生協窓口,ファミリーマート(イープラス) |
| 備考 | 【会場】 黎明館2階第2特別展示室 【開館時間】 9時00分~18時00分(入館は17時30分まで) ※初日は10時開場 【期間中の休館日】 9月29日(月曜日)・10月6日(月曜日)・14日(火曜日)・20日(月曜日)・27日(月曜日) 【展示の構成】 ■序章南九州と南島(なんとう) 南九州と島嶼(とうしょ)世界との交流は,古くは奄美や沖縄で発見される南九州の縄文土器,弥生~古墳時代の遺跡から出土するゴホウラやイモガイなど南海産の貝製品に見ることができます。平安時代にはヤコウ貝,檳榔(びんろう),赤木(あかぎ)など南島産物が,南九州の支配層から都の有力貴族への贈り物とされるなど,南九州は,琉球列島と古代日本を繋ぐ「ひと・もの・文化」の交流の窓口となっていました。 ※南島・・・琉球列島のこと ■第一章東アジア世界と日宋貿易 古代以来,我が国の対外交渉の中心であった大宰府鴻臚館(こうろかん)は11世紀前半に終焉(しゅうえん)を迎えます。 代わって宋から来航する商人たちは博多に住居を構え貿易を営み,ここに「国際交易都市」博多が誕生します。博多遺跡群から出土する貿易陶磁は,他を凌駕(りょうが)する圧倒的な物量を誇り,宋商の日用品,容器として持ち込まれた陶器の甕(かめ)や壺,目印に墨書(ぼくしょ)が記された陶磁器など,港湾都市ならではの多彩な資料が目を見張らせます。博多遺跡群を中心に,九州西岸の中世遺跡,交易船の積荷とされる奄美大島宇検(うけん)村の倉木崎(くらきざき)海底遺跡の貿易陶磁など,日宋貿易に関わる資料を展示します。 ■第二章中世の都市と町 院宮王臣家(いんぐうおうしんけ。皇族や五位以上の貴族)や有力寺社が集まる京は,海を渡って招来される「唐物」が集まる最大の消費地でした。治承・寿永の戦乱(1180~1185)を経て,源頼朝が幕府を開いた鎌倉は新たな政治都市に生まれ変わり,宋・元代の白磁や青磁の優品が集まります。 歴史上の出来事に彩られた京都や鎌倉出土の貿易陶磁,瀬戸内海に注ぐ芦田川の河床から甦った中世の町草戸千軒町(くさどせんげんちょう)遺跡の人々の暮らしを映しだす出土資料を紹介します。 ■第三章カムィヤキ・石鍋・貿易陶磁~平安時代後期の奄美・沖縄と南九州 『新猿楽記』に登場する八郎真人(はちろうのまひと)は,「東は俘囚(ふしゅう)の地(蝦夷=北海道)に至り,西は貴賀の島(奄美諸島)に渡る。交易の物,売買の種,数をあげるべからず。」とあるように列島を勇躍した中世の商人です。11・12世紀,喜界島の城久遺跡群はその盛期を迎え,徳之島伊仙町で生産されたカムィヤキは先島諸島にまで流通します。南九州では島津荘や大隅正八幡宮領の荘園が拡大し,阿多郡司として勢威をふるった阿多忠景は,永暦元(1160)年ごろ追討を受け「貴海島」(『吾妻鏡』)に逃れています。 南さつま市の持躰松(もったいまつ)・渡畑(わたりばた)・芝原遺跡,大隅正八幡宮社家跡など注目される遺跡も紹介します。 ■第四章鎌倉時代の交易・支配と蒙古襲来 鎌倉時代,島津氏,渋谷氏,二階堂氏など諸国に所領を有する有力な関東御家人が守護・地頭として南九州の歴史に登場します。平氏政権の積極的な対外政策は,対外交易の構図に変化をもたらし,蒙古襲来の衝撃にも関わらず,宋末から元代の交流は益々盛んになります。 執権として代々幕府の実権を掌握した北条氏一門は,日元の貿易にも深く関わり,千竃(ちかま)氏を通じて南九州・琉球列島の交易支配にも関わったとされます。鎌倉時代の交易・交流に関わる遺跡や文書のほか,弘安の役で沈没した元船の発見で知られる鷹島(たかしま)海底遺跡などを紹介します。 ■第五章南からの風~グスク時代の奄美・沖縄 南北朝の争乱期,南九州各地に築かれた中世山城からは明代の中国産陶磁器の他,タイ産やベトナム産の陶磁器も出土し,戦乱の時代,海外との交易を求めた領主層の姿を浮かび上がらせます。 14世紀には今帰仁(なきじん)城や勝連(かつれん)城に石積みのグスクが築かれ,沖縄を起点とする新たな対外交易が発展します。1429年には中山王尚巴志(しょうはし)によって三山が統一され,琉球王朝は繁栄の時を迎えます。 南九州の中世山城と奄美・沖縄のグスク,鹿児島神宮所蔵の伝世の陶磁器,琉球王府首里城京の内跡出土陶磁器など珠玉の逸品もお楽しみください。 |
| 関連URL | ・「南からみる中世の世界」リーフレットPDF http://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/kouza/jisyukikaku/kikaku_tokubetutenji/documents/40934_20140820155455-1.pdf |
情報更新日:14/09/16
鹿児島の1ヶ月以内に開催されるイベント情報
イベント一覧鹿児島のイベント情報を検索!
★イベントを探したい日付をクリックしてください!