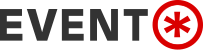利休・剣仲・織部の時代―天正から慶長の書と茶陶―
※掲載中の情報は調査時の情報となります。
※必ず公式サイトなどで最新の情報をご確認ください
- ★開催日・期間
- 2014年04月22日(火)〜2014年06月08日(日)
- ★開催場所・会場
- 野村美術館(京都府京都市左京区南禅寺下河原町61)
この展覧会では3人の茶人千利休や藪内剣仲、古田織部ゆかりの書や茶碗を中心に、桃山時代の茶の湯の美術を紹介します。利休、剣仲、織部の生きた16世紀後半から17世紀初頭、天正から慶長年間の時代は、一般には桃山時代と呼ばれ、豪華絢爛の時代。その一方で、茶の湯では千利休が侘び茶を大成し、古田織部がさらに展開させた時代といわれます。千利休は現在の三千家の祖、藪内剣仲は利休と親しい茶人で織部の妹の婿であり藪内流の祖、古田織部は利休の高弟で織部流の祖です。利休と剣仲、織部は、お互い大変親しく交わり、近しい美意識や価値観を持っていたようです。それは一言でいうならば侘数寄といえるでしょう。しかし時代は、戦争からも伝統からも解き放たれエネルギーに満ち満ちています。その活気のなかでの茶の湯の侘数寄はどのようなものなのか。今回の展示では、長次郎の楽茶碗にみる無駄を省いた端正さ、織部や伊賀にみる表現の力強さ、おもしろさをみていただければと思います。その一方で利休や剣仲ゆかりの品々を中心に当時の茶道具を補って取りあわせを復元しています。桃山という時代の中での利休・剣仲・織部の目指した茶の湯を感じてもらえれば幸いです。
| 開催地 | 野村美術館(京都府京都市左京区南禅寺下河原町61) |
|---|---|
| 開催期間 | 2014年04月22日(火)〜2014年06月08日(日) イベントによっては、期間中でも休みの日がある可能性があります。必ず公式ページでご確認ください。 |
| ホームページ | http://www.nomura-museum.or.jp/ |
| お問い合わせ先 | 075-751-0374 |
| 備考 | 【開催時間】 午前10時~午後4時30分 ※入館は午後4時まで |
| 関連URL | http://www.museum-cafe.com/exhibition?event_id=32883 |
情報更新日:14/03/13
千利休(せん の りきゅう、せん りきゅう、大永2年(1522年) - 天正19年2月28日(1591年4月21日))は、戦国時代から安土桃山時代にかけての商人、茶人。
わび茶(草庵の茶)の完成者として知られ、茶聖とも称せられる。また、今井宗久・津田宗及と共に茶湯の天下三宗匠と称せられた。
名・号
幼名は与四郎(與四郎)、のち法名を宗易(そうえき)、抛筌斎(ほうせんさい)と号した。
広く知られた利休の名は、天正13年(1585年)の禁中茶会にあたって町人の身分では参内できないために正親町天皇から与えられた居士号である。考案者は、大林宗套、笑嶺宗訢、古渓宗陳など諸説がある。いずれも大徳寺の住持となった名僧で、宗套と宗訢は堺の南宗寺の住持でもあった
...「千利休」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』
2014年3月11日06:46 UTC
http://ja.wikipedia.org/wiki/千利休
京都の1ヶ月以内に開催されるイベント情報
イベント一覧京都のイベント情報を検索!
★イベントを探したい日付をクリックしてください!