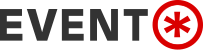2014年9月7日(日) 岩絵の具つくり体験
※掲載中の情報は調査時の情報となります。
※必ず公式サイトなどで最新の情報をご確認ください
- ★開催日・期間
- 2014年09月07日(日)
- ★開催場所・会場
- 奇石博物館(静岡県富士宮市山宮3670番地)
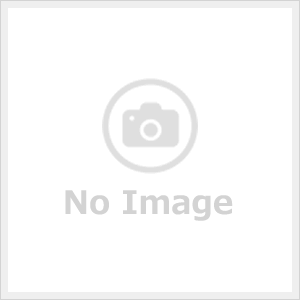
終了その他のイベント
日本画家の橋本弘安氏を講師に招き、古来より日本画などに利用されていた岩絵の具について学びます。また、様々な岩石や鉱物を砕いてオリジナルの岩絵の具を作り、出来上がった岩絵の具の試し描きも行います。
| 開催地 | 奇石博物館(静岡県富士宮市山宮3670番地) |
|---|---|
| 開催期間 | 2014年09月07日(日) |
| ホームページ | http://www.kiseki-jp.com/japanese/event/work%20shop.html#sp2 |
| 料金 | 1人500円(資料、材料費) |
| 備考 | 体験場所;奇石博物館 時間;未定 集合場所;奇石博物館 研究学習棟2階教室。解散も同場所 講師;橋本弘安氏(日本画家、女子美術大学教授) 対象;小学校高学年~大人。(※低学年生以下の方には、親御さんが付き添って下さい。) なお、教室が狭いため、参加者&付添者以外の方の見学はお断りいたします。ご了承ください。 定員;25名(先着順,定員になり次第締め切り) 持ち物;汚れても良い服装、タオル、雑巾、筆記具など 天候;屋内ですので、雨天の場合でも行います 申し込み方法; 実施日の1ヶ月前から募集開始。実施日の3日前までに電話にて事前予約を行って下さい。 その際、参加される方の氏名(付添者がいる場合は、その方の氏名)、年齢(学年)、住所、電話番号をお知らせ下さい。 TEL;0544-58-3830 注)上記の行事予定の日時は、予告なく実施日等を変更する場合があります。 必ず博物館にてご確認下さい |
情報更新日:14/04/11
岩絵具(いわえのぐ)とは、日本画材料として供給されている顔料。 辰砂、孔雀石、藍銅鉱、ラピスラズリなど様々な鉱石、半貴石を砕いて作った顔料を頂点とする。番手の粗いものには結晶形が明瞭なものも、辰砂や石黄など幾つかあり、多くは粗粒が構成する様相が特徴的である。
粉末状の顔料(絵具)であり固着力がなく、単独では画面に定着しない。伝統的には、固着材として膠(ニカワ)を併用し、指で混ぜて練成する。 粉末の目の細かさは番数で分別されており、一般的には、5番~13番、白(びゃく)とあり、数字が大きくなるほど粒子が細かくなる。 細かい粒子になるほど粒子表面の乱反射が多く白っぽくなり、逆に粗いほど暗色になる性質を利用し、同じ組成を有する岩絵具でも色合いが異なるものが供給される。異なる粒子径で同様の色合いを求める場合、粉砕とは別の工夫を要する。
京都府が一大消費地である。大手メーカーとしてナカガワ胡粉絵具株式会社(宇治市)があり、伝統的な胡粉を製造している。ハマグリ胡粉はホルベイン工業株式会社が供給している。
「岩絵具」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』
2012年9月07日08:20 UTC
http://ja.wikipedia.org/wiki/岩絵具
静岡の1ヶ月以内に開催されるイベント情報
イベント一覧静岡のイベント情報を検索!
★イベントを探したい日付をクリックしてください!