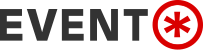井上安治生誕150年記念 絵師たちの視線(まなざし) ―安治・清親・光逸―
※掲載中の情報は調査時の情報となります。
※必ず公式サイトなどで最新の情報をご確認ください
- ★開催日・期間
- 2014年04月27日(日)〜2014年06月08日(日)
- ★開催場所・会場
- 茅ヶ崎市美術館
春季の企画展では、生誕150年となる夭折の絵師・井上安治(いのうえ・やすじ 1864~1889)の代表作である〈東京真画名所図解〉を中心に、その師である小林清親(こばやし・きよちか1847~1915)と安治の弟弟子となる茅ヶ崎ゆかりの土屋光逸(つちや・こういつ 1870~1949)の作品を紹介します。
最後の浮世絵師ともよばれた小林清親は、1876(明治9)年の夏から、のちに〈東京名所図〉と総称される木版風景版画を刊行しました。これらは従来の浮世絵の表現とはまったく異なり、遠近法や陰影法など西洋絵画的な空間表現をとりいれた斬新な画風であったため好評を博しました。井上安治は清親が〈光線画〉ともよばれた〈東京名所図〉の連作により新時代の人気絵師として活躍していた1878(明治11)年、最初の門人として清親に師事します。その後、1880(明治13)年6月、数え17歳の安治は師の後援を得て3点の木版風景版画を刊行して世に出ました。そして翌1881(明治14)年、この年に師・清親がふっつりとその制作をやめた〈東京名所図〉を引き継ぐように〈東京真画名所図解〉連作の刊行を開始します。
〈東京真画名所図解〉は総数130図を超える組物で、その多くは葉書ほどの大きさであり、全体の五割弱は師・清親の〈東京名所図〉に酷似した構図が用いられています。しかし、師の構図にそった作品であっても、画面を小型化する際になされるモチーフの取捨選択や背景の処理などに個性を表しています。また、安治自身の構図による作品も含め、画面から滲み出る情趣には独自のものがあります。
今回の展覧会では井上安治の〈東京真画名所図解〉134図のほか、小林清親の〈光線画〉作品や師風を継いで夜景を得意とした土屋光逸の代表作〈東京風景〉(全12点)などを展示し、伝統的な技法によりながらも新しい表現方法をもちいて風景を探求した絵師たちの仕事を紹介します。
| 開催地 | 茅ヶ崎市美術館 |
|---|---|
| 開催期間 | 2014年04月27日(日)〜2014年06月08日(日) イベントによっては、期間中でも休みの日がある可能性があります。必ず公式ページでご確認ください。 |
| ホームページ | http://www.chigasaki-museum.jp/exhi/2014-0427-0608tenrankai/ |
| 料金 | 一般:300円(250円) 大学生:200円(150円) 高校生以下:無料 市内在住65歳以上・市内在住障害者およびその介護者は無料 ※( )内は20名以上の団体料金 |
| 備考 | 【休館日】 4月28日(月)、30日(水)、5月7日(水)、8日(木)、9日(金)、5月12日(月)、13日(火)、19日(月)、26日(月)、6月2日(月) 【開館時間】 10:00~18:00(入館は17:30まで) 【会場】 茅ヶ崎市美術館 展示室1・2 ※関連イベントとして「ミニコンサート」や「ゲストトーク」などが企画されています。詳しくはホームページでご確認下さい |
情報更新日:14/04/15
井上 安治(いのうえ やすじ、元治元年(1864年) - 明治22年(1889年)9月14日)は、明治時代前期の浮世絵師、版画家。名前はやすはると読むとする説もある。本名は安次郎。作品によっては安次、安二、安二郎、安はると署名し、探景とも号した。
小林清親の一番弟子とされ、短命であったが光線画に優品を残した。
生涯
生い立ち
井上清七の長男として浅草並木町(今の雷門二丁目)で生まる。父は川越鍛冶町(現・幸町)にあった高麗屋という錦織問屋(太物仲買商)に生まれたが、江戸に出て浅草駒形町にあった丸屋呉服店に勤め、のちに一番番頭となっている。兄弟は姉と弟がおり、13歳の時父が亡くなってからは母の手ひとつで育てられたようだ。
幼児より病弱で絵を好み、少年の頃
...「井上安治」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』
2014年2月23日10:47 UTC
http://ja.wikipedia.org/wiki/井上安治
神奈川の1ヶ月以内に開催されるイベント情報
イベント一覧神奈川のイベント情報を検索!
★イベントを探したい日付をクリックしてください!